
循環器内科・ペースメーカー外来

循環器内科・ペースメーカー外来
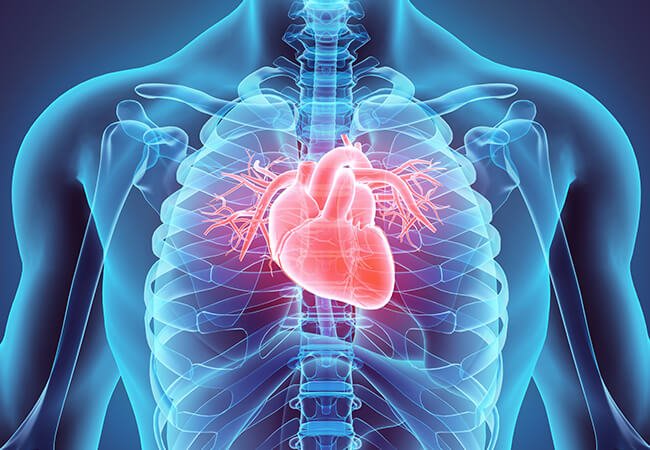
循環器内科では、全身に血液をめぐらせる心臓や血管の病気を専門的に診療します。
狭心症・心筋梗塞、心臓弁膜症、心不全、不整脈などの心臓の病気や、動脈硬化症、動脈瘤などの血管の病気に幅広く対応しています。
当医院院長は、八尾、柏原などの基幹病院での経験を通じ、心臓病の早期発見と治療に力を注いでおり、特に不整脈、心房細動の治療、その合併症としての脳梗塞の予防、心不全の予防、ペースメーカー管理など循環器専門医としての長い治療経験から一層力を入れて取り組んでいます。
心臓病は、発見や治療が遅れると手遅れになることがあり、日常生活に大きな影響を与えることがあります。また、循環器疾患は原因となる高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙習慣などを総合的に管理しながら治療を行うことが大切です。
当院では循環器疾患の予防と早期発見、診断と治療、慢性期における再発防止など、提携医療機関との充実した医療体制のもと行っております。
気軽に相談できる“心臓と血管のかかりつけ医”としてお役に立てましたら幸いです。
心臓や血管などの病気に関して専門的な診療を行っております。
このような症状やお悩みがある方はご相談ください
日常的に起こりやすい症状でも、詳細な検査を行うことで重大な病気の早期発見につながることもよくあります。気になることがございましたら、何でもお気軽にご相談ください。
心臓の冠動脈が動脈硬化などによって狭くなると、心筋(心臓壁を構成する筋肉)に送られる血液量が不足し、心筋が酸素不足となります。このときの痛みが狭心症の痛みです。
労作性狭心症は「階段を上ると胸が締めつけられるように痛くなる」、「重いものを持ち上げたり、坂道を歩いたりすると胸が苦しく痛む、安静にすると楽になる」という症状がみられます。痛みの特徴としては圧迫感や絞扼(こうやく)感などがあり、前胸部、みぞおち、肩、頸などに生じます。歯やのどが痛むケースもあります。痛みは多くの場合、数分までです。
安静時狭心症は、夜、就眠中、明け方に胸が苦しく押さえつけられたような発作が起こります。多くの場合、冠動脈が一過性に痙攣(けいれん)を起こして収縮し、血流が一時的に途絶えるために生じると考えられています。冠攣縮性狭心症ともいいます。痛みの性質や部位などは労作性狭心症と同様です。冠動脈の攣縮(痙攣性の収縮)も、動脈硬化の進行過程にみられる現象と考えられています。
このような症状がある場合、早めに検査を受けることが大切です。
心筋梗塞とは、動脈硬化が進行して冠動脈にできていたプラーク(血液中のコレステロールや脂肪からできた粥状の物質)が冠動脈を塞いでしまい、心筋に血液が完全に行かなくなり、心筋が壊死した状態をいいます。突然、胸が焼けるように重苦しくなり、締め付けられ押しつぶされるような症状が現れます。冷や汗が出たり、吐き気があったりすることもあります。この発作は長く続き数時間に及ぶこともあります。このような場合は、至急救急車を呼んでください。内科的治療は冠動脈内に詰まった血栓を、血栓溶解薬(tPAなど)で溶かす治療法や、バルーンが先端についたカテーテル(細い管)を血管内に挿入し、詰まった部分を拡げたり、再閉塞を防ぐためにステント(筒状の金網)を血管内に留置したりするインターベンション治療があります。
心臓弁膜症とは心臓にある弁に障害が起き、本来の機能や役割を果たせなくなった状態をいいます。大きく分けて、弁の開きが悪くなり血液の流れが妨げられる「狭窄」と、弁の閉じ方が不完全なために血流が逆流してしまう「閉鎖不全」があります。
典型的な症状は、息切れ、胸の痛みや違和感、めまい、意識を失う、疲れやすいなどがありますが、心臓弁膜症に特有なものはありません。症状があっても加齢に伴う体の変化に似ていることから、見逃されがちです。
「健康診断などで心雑音が指摘された」、「心エコー図検査で心臓弁の異常を指摘された」という場合には、早めに専門医を受診しましょう。
心臓は全身に血液を送り出すポンプの働きをしていますが、心筋梗塞や心臓弁膜症、心筋炎など様々な心臓の病気によって、このポンプの働きに障害が生じ、色々な症状を引き起こしている状態をいいます。「急性心不全」と「慢性心不全」に分けられ、急性心不全は、短期間で激しい呼吸困難などの症状が現れることから、重症の場合、命を失う危険性が高くなります。一方、慢性心不全は、ちょっとした動作でも動悸や息切れがしたり、疲れやすくなったりします。咳や痰が止まらない、むくみが出るといった症状が現れることもあります。
慢性心不全は生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)との関連性が高く、高齢になるほど発症する方が増えてくる傾向があります。
主に足の血管に起こる動脈硬化で、末梢動脈疾患とも呼ばれています。足に冷感やしびれ、歩行時に痛みを感じる、という症状があり、重症化すると手足に潰瘍ができ壊死することもあります。特に50歳以上の男性に多い傾向があり、肥満・高血圧・糖尿病・喫煙などが原因と考えられています。閉塞性動脈硬化症を発症した場合には、下肢動脈だけでなく全身の血管も動脈硬化が進んでいる可能性が高いので注意が必要です。
不整脈は、脈が飛ぶ・乱れる、脈が不規則になる、頻脈(脈が速くなる)、徐脈(脈が遅くなる)など、脈の拍動に異常がある状態を広範囲に意味します。心臓は規則正しい電気信号によって刺激され、規則正しいリズムで拍動します。不整脈は、発生する電気に異常があるか、電気が伝導路をうまく流れないために起こる状態です。不整脈は治療の必要のないものから危険なものまで様々です。不整脈は健康成人では一般的で、不整脈がありながらご自身で気付かず、身体検査などではじめて不整脈を指摘される方もいます。一方、不整脈によっては心不全や失神発作を起こしたり、脳梗塞を併発したりするものもあります。不整脈を指摘されたときや脈の不整、激しい動悸を感じたときは専門医を受診しましょう。放置しておいてもよい不整脈なのか、危険な不整脈に発展するものかなど、よく説明を聞いて適切な指導を受けることが大切です。
心電図は、健康診断を含め、心疾患の早期発見と診断のために行われます。動悸、胸痛、ふらつきなどの原因を調べるためにも行います。
患者様は診察台に横たわり、12か所のポイントで心電図を記録し、不整脈や心筋障害の有無を調査します。ただし心疾患が存在する場合でも、いつでも心電図に異常が現れることはまれであり、この検査だけでは見逃されることもあります。
また一度の検査で異常が発見されない場合があります。その場合は、発見の可能性を高めるために24時間心電図検査(ホルター心電図)を行うこともあります。
携帯型の記録機を使い、胸部に電極を貼って心電図を24時間連続撮影します。24時間測定することで、睡眠中や日常生活中の異常や発作を特定することが可能になります。不整脈の経過や治療薬の効果を確認するためにも欠かせない検査です。
レントゲン検査は、健康診断でも肺や心臓に異常がないかを調べるために行います。
心陰影の拡大の有無、心不全の程度、胸水や肺炎がないかなどをみます。また、息切れや胸痛の原因を特定するためのスクリーニングで行います。
「足の動脈の詰まり」を判定するABI(足関節上腕血圧比)と「血管の硬さ」を判定するPWV(脈波伝播速度)を測定することで、動脈硬化を調べる検査です。
簡便な検査であり、閉塞性動脈硬化症の診断でまず行います。
ABI(足関節上腕血圧比)とは、足首の血圧を上腕の血圧で割り算をし、動脈の狭窄の程度を判定する検査です。足首の血圧は上腕の血圧より高いのが正常です。しかし、動脈硬化によって足の血管が狭くなったり詰まったりすると、足首の血圧は上腕の血圧より低くなります。この仕組みを利用した検査です。0.9以下で下肢動脈の狭窄が疑われるので下肢エコーや造影CT検査をお勧めします。PWV(脈波伝播速度)とは、心臓から押し出された血液が生み出す拍動が血管を通って手や足に到達する速度のことです。血管が硬いほどこの速度が速くなる仕組みを利用し、「血管年齢」を割り出すことが可能になります。
超音波検査によって、心不全とその程度、心筋梗塞の有無、心肥大や拡大、弁膜症、先天性疾患などが発見できます。また、治療法の選択、治療効果の判定、手術時期の決定にも有益です。
頸動脈は脳に重要な血流を供給する動脈であり、その動脈の硬化による狭窄や、脳梗塞や脳塞栓症などの脳血管障害を引き起こす血栓の有無を検査します。頸動脈の動脈硬化が進行すると、その他の部位、例えば大動脈や心臓の冠動脈などにも動脈硬化が及んでいることが示唆されます。そのため全身の動脈硬化の程度を判断するのにエコー検査は役立ちます。この検査は特に、脂質異常症、糖尿病、高血圧、喫煙者などの患者様に有益です。
ペースメーカー治療を受けておられる方は、定期的に大きな病院で診察に行かれることがご負担となっていると思います。院長も勤務医時代はペースメーカーのチェックだけに長い待ち時間がある病院に来られる患者様に申し訳なく思い、当院でもペースメーカーの診察が可能となっております。
心臓は4つの部屋(左心房、右心房、左心室、右心室)からなり、電気信号によって全身に血液を送り出すポンプ機能を担っています。洞結節(どうけっせつ)から電気信号を発生し、右心房を通って房室結節(ぼうしつけっせつ)という場所に伝わることで心室が収縮を行います。脈が病的に遅くなる「徐脈(じょみゃく)」は、この収縮にかかわる「洞結節」と「房室結節」に異常が起こることが原因と考えられています。
洞結節の疾患である洞不全症候群は、右心房の洞結節の細胞に異常が生じて、心臓を動かす電気の発生回数が極端に減少したり、発生できなくなったりします。
房室結節の異常には房室ブロックがあります。洞結節で発生した電気は心房を収縮させると、房室結節を経由して、次に心室を収縮させます。この房室結節の細胞が何らかの異常を起こし、電気信号が心室にうまく伝わらなくなった状態が房室ブロックです。
これらの徐脈性不整脈では、心臓の筋肉に人工的な電気信号の刺激を与えて、心収縮を発生させる必要があります。ペースメーカーは、この目的を達成するために用いられる医療機器です。
電気パルスを発生させるペースメーカー本体は小さな金属製で、リチウム電池と電気回路が内蔵されており、重さは20g前後です。継続的に心臓の動きをモニターし、遅い脈拍(徐脈)を検知したら、微弱な電気刺激を送って正常な脈拍に戻します。
ペースメーカーの手術は、基本的に左右いずれかの鎖骨下の前胸部分を、4~5センチ程度切開し、皮膚と筋肉の間に埋め込みます。リードと呼ばれる電線は、血管を通して心臓内(右心房と右心室)に留置します。多くの場合、局所麻酔にて施行可能ですが、場合により全身麻酔下で行うこともあります。
リードを必要とせず、小さな電池本体のみでペースメーカーの機能を持つリードレスペースメーカーもあります。
このデバイスは、本体は皮下に埋め込むのではなく、カテーテルを用いて直接心臓内に留置します。
徐脈性不整脈は、脳や他の臓器へ送られる血液の量が減り、息切れ・めまい・眼前暗黒感(目の前が暗くなる感覚)・意識消失などの症状を引き起こします。
徐脈は加齢や動脈硬化が進んでいる方に起こりやすいといわれています。そのほかに虚血性心疾患、高血圧症、先天性心疾患、心筋症なども原因として挙げられます。慢性腎機能障害による電解質異常や甲状腺疾患、高血圧治療薬や精神疾患治療薬などの薬剤によって起こることもあります。徐脈はすぐに命に関わることは少ないため、重大な自覚症状がなければ経過観察となります。ペースメーカーによる治療が検討されるケースは次のような場合です。
ペースメーカー外来では、自覚症状や心電図所見をもとに、専門医がペースメーカー治療の適応を判断します。ペースメーカー移植術が必要な患者様は近隣の総合病院にご紹介させていただきます。
ペースメーカーは心臓の働きに関わる精密機器であるため、術後のペースメーカー管理も重要で、定期的にしっかり点検する必要があります。
当院では、脈が遅くなる徐脈性不整脈(洞機能不全症候群、房室ブロック、徐脈性心房細動など)の治療でペースメーカーを埋め込んだ患者様に半年ごとの定期点検を行っています。
点検は専用の機械を体表面に当てて行うもので、身体への負担はほとんどありません。点検内容は、ペースメーカーの動作確認、電池残量の確認(5~10年に1回程度の電池交換が必要になります)、リード線の異常の有無、不整脈や心不全の状況確認などを行います。必要に応じてプログラムを微調整し、本体の交換が必要であれば入院予約をします。
点検前には心電図や胸部レントゲン検査を行い全身の状態も診療します。
定期的なチェック以外にも、めまいや動悸など、気になる症状があった場合には、念のためペースメーカーのチェックをお勧めします。安心して受診していただけるよう、丁寧な説明と治療計画の提供を心がけています。どんな小さな疑問や不安でも、お気軽にご相談ください。
電話回線を通じて自宅に居る患者様のペースメーカーデータを収集し、当院からそのデータを閲覧することができる仕組みが整っています。遠隔モニタリングによって、心不全や不整脈の状態、ペースメーカーの異常などを早期発見することが可能です。
TOP